2015/11/25 12:02
栃木県宇都宮市で設計を進めていた工場(事務所・ショールームを含む)が着工しました。
現在、基礎補強工事、1工区の基礎配筋検査が終わり、コンクリート型枠を組んでるところで、2016年春頃に竣工予定です。当分宇都宮に通うことになります。


敷地面積9400㎡,延床面積2600㎡,鉄骨平屋
意匠:SPACESPACE 構造:オーノJAPAN 設備:島津設計
栃木県宇都宮市で設計を進めていた工場(事務所・ショールームを含む)が着工しました。
現在、基礎補強工事、1工区の基礎配筋検査が終わり、コンクリート型枠を組んでるところで、2016年春頃に竣工予定です。当分宇都宮に通うことになります。


敷地面積9400㎡,延床面積2600㎡,鉄骨平屋
意匠:SPACESPACE 構造:オーノJAPAN 設備:島津設計
練習量もほとんどない上に、21チームのうち半数程度が学生中心のチームという中、平均年齢高めのソレッテ大阪?が4位になったわけ。
それはチームワークの良さにつきます。
とは言っても、今回参加したメンバー23(内3歳児一人)人中、6人は東京で働くOB。1人は東京で大学院に通うOB。会うのも、短くて1年ぶり。
そして今年はなんと、デンマークで働くOGも緊急来日して参加。という、このA☆CUPがあるからこそ、集まれるメンバー構成なのです。

そして、もちろん、久しぶりすぎて、一日目の夜はなんと朝の4時半まで、近況報告会。。(私はおチビと一緒だったので、渋々早く寝ましたが。。)ずっと一緒にいるチームワークではなく、離れているけど、それそれみんなが頑張っていて、顔を合わせればすぐに一体感をえれるチームワーク。コミュニケーション能力に長けたメンバーだからこそ生まれる環境だと思います。
サッカーはチームワーク。一人で走らず、相手を信じてパスを出す。そういう関係ができているのがソレッテです。
今年も行ってきましたA☆CUP!
よく、「A☆CUPってどこでやってるの?東京?」って聞かれるのですが、違います。東京からまだ遥々北へ向かった茨城県の銚子からまだ少し北に行った「矢田部」というところにあるサッカー場で毎年行われています。
矢田部はほんと海添いで、風が強く、遠景に数多くの風力発電の風車が見えるような場所です。
私の所属する「ソレッテ大阪?」メンバーは東京駅で集合し、そこから鈍行に乗って2時間半かけて銚子まで行きます。そこから宿泊所の送迎バスでサッカー場まで。という、新大阪を9時前に出てサッカー場に着くのが16時、、という7時間半の長時間移動で毎年遠征しています。まぁ、なぜそこまでして??という声も聞こえなくもないのですが、このA☆CUP、建築界にとっては重要なイベントなのです!
年に一回、矢田部に集まって一緒にサッカーをする。もちろん、ガチじゃないサッカー。
A☆CUPにはいろいろな特別ルールがあり、絶対「女子か子供を出さないといけない」、とか「MA(ミドルエイジ)と呼ばれる30歳以上をださないといけない」「OA(オーバーエイジ)と呼ばれる40歳以上を出さないといけない」という、学生だけのガチじゃない、交流試合ができるようなルールになっています。試合時間も15分ハーフ。
前夜祭では、各チームの現在の建築活動についてのプレゼン。日本だけでなく、世界でも活躍している人たちの活動を知る機会でもあります。今年も21チームが集まり、7グループ3チームで、公式戦は予選は2試合と決勝トーナメントを行いました。

ソレッテ大阪?はMA以上の割合がどんどん多くなってきていて、普段は仕事も忙しいので、なかなか練習もできないチームですが、なんと、予選2戦全勝で決勝リーグに進み、なんと、4位入賞でした!
最後の3位決定戦では、PKで負けるという、惜しい結果でした。
試合結果もさることながら、このソレッテというチームが凄いので、またチームの紹介は次の機会に。
週末は地鎮祭のため宇都宮へ。

初めての土地での地鎮祭。やはり、その土地土地によって少しずつ習わしも違うようで、今回もいくつか違う点が。
まず、祭壇ですが、今まで見た地鎮祭では3段程度の祭壇に奉献酒やその他お供え物が飾られているものだたのですが、今日のは木でフレームが組まれた中に祭壇が作られていました。
また、鍬入れの儀では、設計者が鎌だというのは同じだったのですが、施主と施工者が逆で、施主が鍬(くわ)で、施工者が鋤(すき)でした。
これにはびっくり!施主も設計者も施工者もみんな関西なので、この違いには驚いていました。こういった儀式は土地のものなので、その土地土地でちょっとずつ違うみたです。

ブログの更新も久しぶりですがウェブサイトの方も気がつけば更新が滞っているので、ちょっとだけ更新しました。途中で掲載されたメディア等も覚えているものは近いうちにアップします。実施図等に追われ、溜め込み過ぎましたね。。。以下展覧会のお知らせです。
建築家による木造建築模型展に出展します。
会期:2015年10月15日(木)-20日(火) 10:00- 18:00(会期中無休 / 最終日は17時まで)
会場:大阪デザイン振興プラザ デザインギャラリー
(大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10F)
入場料:無料
主催:NPO法人teamTimberize
大阪府地域産材活用フォーラム
一般社団法人大阪府木材連合会
後援:大阪府
協力:大阪木材仲買協同組合
アジア太平洋トレードセンター株式会社
大阪デザイン振興プラザ(大阪市・ATC)
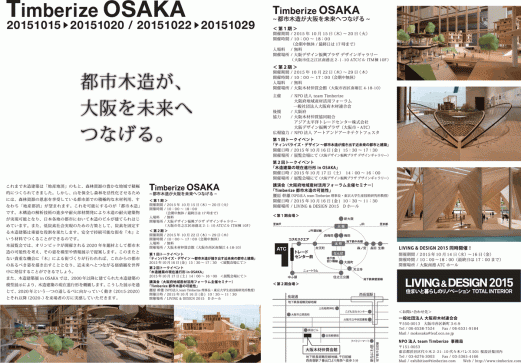
大阪府門真市の介護付有料老人ホームが上棟しました。
施工はDアパートメントと同じくパナホームです。現場の体制も前回とほぼ同じなので、ここまで快調に進んで来ました。ここから屋根・外壁工事に入ります。
1F中庭付近。

屋根。デッキ部分がメンテナンス通路を兼ねた樋。

夏の竣工まで、まだもう一息です。
これを機会に2013年2月から始まった「八木プロジェクト」についてちゃんと書いておこうと思います。
まずは出会い編。八木プロジェクトは2013年2月に、奈良県立医科大学の医大生のサークル「チームPREドクターズ」のメンバー3人が、うちの事務所に相談に来たところから始まります。

(PREドクの三人と後日現地へ行った時の写真)
その相談とは、「学校近くの空町屋を安く借りられそうなので、そこでカレー屋を開きたい。それに向けて町屋を改修したいので、設計のアドバイスが欲しい」とのことでした。
よくよく話を聞いていると、簡単に言ってしまえば、「なんとなくのお店のイメージは持っていて、工事も自分たちでしたい。けれど、技術もないし知識もないから助けて!」と。これは単なる設計依頼ではないことはすぐわかるし、相手は学生。設計料なんて概念は全くない様子(笑)
もちろん、単に技術的なことだけ相談に乗ってサラッと済ませることもできたのですが、彼らのそれまでの活動を聞いているとそのバイタリティに魅力を感じ、じっくり協力せずにはいられなくなりました。
そしてなにより、「医大生」が「自分たちで町屋を改修」することが面白そう!だと思いました。
そんな機会はなかなかないし、町屋にも彼らにもポテンシャルはあるので、それを最大限に生かしてあげたい!私たちも協力する限りは、面白いものにしたい!という気持ちがありました。
そこから、私たちの彼らへのヒアリングと提案がはじまっていきました。次回へ続く。。
今日(2015年4月18日)の毎日新聞朝刊に、SPACESPACEとOCTで取り組んでいる、八木プロジェクトが紹介されました。

おおさか 「まなびやの宝」という記事です。私が取材を受けたのですが、コメントがちょっとだけ最後に載っています。
この記事になっているのは、第一期(2013年2月~2013年8月)についてなのですが、現在第二期として同じ南八木地区の別の町屋の活用に取り組み始めています。
第一期では、活用の方法自体は、うちの事務所と運営者である奈良県立医科大学の学生チーム「チームPREドクターズ」とで決めてからの、OCT学生の参加だったので、OCTの学生は、改修の技術的な部分をサポートする「手足」として協力することになったのですが、第二期は、まだ活用の方法すらなにも決まっていない状況です。
なので、OCTの学生には単なる「手足」ではなく、活用方法を探る段階から一緒に取り組み、「企画」することの面白さと、いろんな分野の人たちと「協同」する楽しさや意義を肌で感じてもらえたらなと思っています。
専門学校というと、やはり「技術を身に着けるところ」というイメージが大きいですが、OCTはそれだけではありません。「モノ」と「コト」の両面から建築やその周辺を考える機会を常につくっています。時代背景から、単に「つくる」だけでなく、「つくるまえに考える。つくられ方を考える」等が必要な職能になっています。そういった職能を、実体験を元に身に着けられるのがこの八木プロジェクトだと思っています。
そういう部分も取材でお話したのですが、文字数が決まった記事になると難しいですね。ということで、補足させてもらいました~。
4月2日、見事に桜満開の中、OCTの入学式がありました。

今年も去年とほぼ同じ人数の学生たちが入学です。彼らのちょっと緊張しながらも期待に満ちたきらきらした目を見ていると、こちらも気が引き締まる思いです。
特に私が主に授業を担当し、昨年から副担任をしている建築設計学科は、リカレント生と言って、社会人経験者や大学卒業者等を対象としているため、学生の気や期待はひとしおです。そんな彼らを教える教員側も責任は重大。
入学式の会場に入る彼らの顔を見て、ますます気を引き締めるとともに、またこの一年、新しい学生たちの出会いにこちらもワクワクドキドキです!
先日、知り合いの人に誘ってもらい、とある演劇?パフォーマンスを観に行ってきました。
それは、パリのビジュアル コミック サーカス・カルテット、ウサギ食べるズの大阪公演『Mélanger! めらんじぇ!』でした。
その人たちがどんな人なのか、どんな公演だったのかはリンクhttp://mangeursdelapin.com/jp/osaka/から。この公演は面白いんですが、なにより、日本の狂言とのコラボっていうのが面白い。そして、その公演には3つのプログラムがあるのですが、私たちが行った公演はキッズ向けプログラムで、同伴の小学生以下1名は無料!そして、内容も会場を巻き込むこの回だけのパフォーマンスということで、息子を連れて行ってきました。
息子にはちょっと早いかな?と思いましたが、リズム感のいい音楽と、言葉がわからなくてもちゃんと伝わってくる笑いの部分と高度なパフォーマンスに 引き込まれたようで、約2時間の公演中、ずっと私の膝の上で、リズムに乗ったり手拍子したりと、楽しんでいました。
そして、公演中何度も流れるウサギ食べるズのテーマ?ソング。 これが、耳につくw うちの子は、いまだに時々思い出して足踏みしながら歌っていますw
こういう、言葉が通じなくても感じられるパフォーマンスっていいなと思いました。ましてや、その国の伝統芸能とのコラボ。 単純に楽しかったし、また、いつか日本公演があればいきたいと思います。